当教室では蛋白尿出現や腎機能悪化・自己免疫性疾患発症のメカニズムについて、患者さんの検体(血液、尿、腎組織など)、遺伝子改変動物、培養細胞を使用して多面的に研究しています。
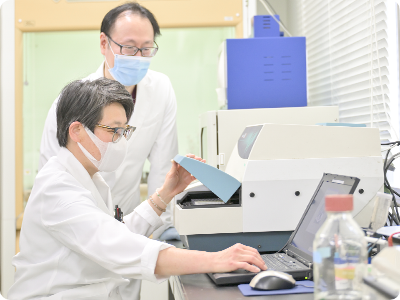
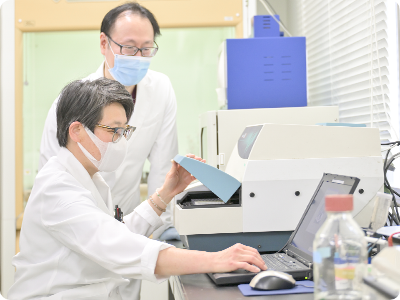
教室スタッフと大学院生がチームを作り、基礎研究を進めています。
浜谷博子助教のグループでは、TGF-βにより糸球体上皮細胞の機能維持に重要な転写因子であるWT1の発現が低下することこれまで報告(Nephrol Dial Transplant 2011, Nephrology 2019)していますが、田部井彬史先生がこの機序におけるmicroRNAの関与を検討し、結果を報告しました(Am J Physiol Renal Physiol. 2023 Jul 1;325(1):F121-F133.)。
渡辺光治先生により、フローサイトメトリー法を利用して、腎単核食細胞と呼ばれる腎に常在するマクロファージや樹状細胞からなる複数の亜群を詳細に解析する方法を開発して、Biochem Biophys Rep.に2020年に発表しました(Biochem Biophys Rep. 2020 Mar 4;22:100741.)。
現在、この解析方法を用いて、樹状細胞特異的SHP-1欠損マウスにおいて生じる尿細管間質障害機序の解明を行い、論文投稿準備中です。
諏訪絢也先生と今井陽一先生はマウス腎組織から尿細管間質線維芽細胞を渡辺先生が開発した手法を用いて分画し、腎線維化機序を解明することをテーマに研究を進めています。
木下雅人先生は、樹状細胞特異的SHP-1欠損マウスが涙腺炎、唾液腺を自然発症しシェーグレン症候群のモデルマウスにもなることを見出しました。2020年の欧州リウマチ学会で発表し、現在論文投稿準備中です。
本マウスは耐糖能障害が生じることも判明しており、大学院生のShrestha Shreyaさんが2019年の日本免疫学会で発表し、現在論文投稿中です。
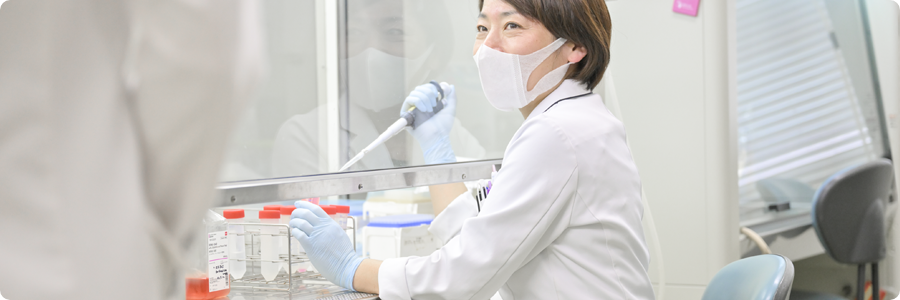
全国の医療機関・施設と共同、あるいは当科での診療成績を元に腎臓・リウマチ性疾患の臨床研究を継続して行っています。特にループス腎炎に関しては腎疾患・リウマチ性疾患両者のエキスパートである当科の特色を十二分に生かし、世界的にも注目されている研究が進行中です。MMFとTACを併用したマルチターゲット療法の報告(Mod Rheumatol. 2014 Jul;24(4):618-25.)に関しては、2019年のヨーロッパリウマチ学会でのループス腎炎診療ガイドラインでも当科の治療成績が引用されています (Ann Rheum Dis 78 : 736-745, 2019.) 。現在今井陽一先生によりマルチターゲット療法の長期予後および治療抵抗性因子に関し解析を進めており、投稿準備中です。ループス腎炎に対するベリムマブの第3相試験であるBLISS-LNのサブ解析に関しても廣村教授が共同著者として関わりました(Nephrol Dial Transplant. 2023 Nov 30;38(12):2733-2742. )。
日本腎臓学会の腎生検レジストリの二次研究で、国内のループス腎炎患者の解析を行い発表しています(Nephrology (Carlton). 2017 Nov;22(11):885-891., Clin Exp Nephrol. 2022 Sep;26(9):898-908.)。
諏訪絢也先生によりループス腎炎の新規尿中バイオマーカーの検討を行っており、成果の一部を名古屋大学との共同研究として発表しています(Kidney Int. 2019 Mar;95(3):680-692. )。
医療の質・安全学病院助教の大石裕子先生が当科のSLE患者約100件の妊娠転帰をまとめました(Clin Exp Nephrol. 2021 Aug;25(8):835-843. )。
田部井彬史先生が当科でのANCA関連血管炎(AAV)のデータベースを構築する過程で、ANCA関連血管炎に伴う中耳炎(OMAAV)の患者30例の臨床像と経過を報告し、聴力予後に関連する因子まとめ報告しました(Mod Rheumatol . 2022 Aug 20;32(5):923-929.)。
その他、ANCA関連血管炎に関してはリツキシマブによりステロイド使用量の減量を図ったLoVAS試験を他施設共同で行い、成果を発表しています(JAMA. 2021 Jun 1;325(21):2178-2187.)(Ann Rheum Dis. 2024 Jan 2;83(1):96-102.)。